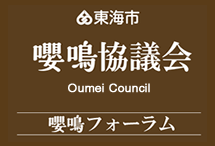生涯学び続けることの大切さを説いた佐藤一斎の三学の精神を理念とし、読書のすすめ、求めて学ぶ、学んで活かすの三つの柱からなる、市民三学運動に取り組んでいます。「生涯学習都市三学のまち恵那宣言」を制定し、市を挙げて生涯学習のまちづくりを進めています。
位置
岐阜県南東部に位置し、愛知県と長野県に隣接している。周囲を標高800m~1,200m前後の山々が連なり、市街地の北部を木曽川が、南端を矢作川が流れ、美しい山や川に囲まれている。名古屋市から1時間の距離にあり、中央自動車道、JR中央線などが通る。
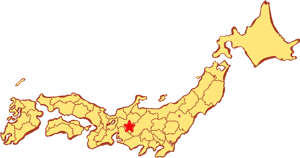
基本情報
| 面積 | 504.24 km² |
| 人口 | 45,547人(令和7年9月1日現在) |
| 市長 | 小坂喬峰(こさか・たかね) |
| 由来 | 平成16年(2004)10月25日恵那市、岩村町、山岡町、明智町、串原村および上矢作町が新設合併して恵那市が誕生。 |
| 市名のいわれ | 律令制の郡名「恵奈郡」に由来する。初見は、天武6年(677年)。明日香村出土の木簡に恵奈と書かれていた。 |
| 産業 | 自動車部品などの機械器具・精密加工、板紙・段ボールなどの厚紙の製造・加工がある。JR恵那駅が恵那峡への観光の入口になっており、国の重要伝統的建造物群保存地区を中心とした岩村町の町並みや明智町の日本大正村などおもてなしの心で迎える観光交流にも力を入れている。 |
| 特産品 | 栗菓子、五平餅、細寒天(生産量は全国第1位)、シクラメン(栽培発祥の地) |
| ホームページ | http://www.city.ena.lg.jp/ |
| 市民憲章 | わたくしたち恵那市民は |
| 一 仕事にはげみ 豊かなまちをつくりましょう | |
| 一 自然を愛し 美しいまちをつくりましょう | |
| 一 教養をたかめ 文化のまちをつくりましょう | |
| 一 きまりを守り 住みよいまちをつくりましょう | |
| 一 お互いに助け合い 明るいまちをつくりましょう | |
| (平成16年10月25日制定) |
ふるさとの先人

.jpg)

.jpg)
ふるさとの先人を活かした主な活動
「三学の精神」に学ぶ
佐藤一斎『言志晩録』第60条
少にして学べば 則ち壮にして為す有り
壮にして学べば 則ち老いて衰えず
老いて学べば 則ち死して朽ちず
(社会に役立つ有為な人になろうとの高い志を抱いて学び続ければ、その精神は朽ちることがない。より良い自分を目指して生涯学び続ける人は、いつまでも人の心に残る人になる。)
これは岩村藩出身の儒学者佐藤一斎が、生涯学び続けることの大切さを説いた教えで「三学戒」と呼ばれています。恵那市ではこれを「三学の精神」を捉えて、生涯学習のまちづくりを進める理念としています。
生涯学習都市「三学のまち恵那」宣言
四季を彩る里山 清き水の流れ
豊かな時をつなぐまち 恵那
このまちに生きて
書を読み 人に学び
歴史と文化 自然に学び
学び続ける 喜びをひろげ
希望あふれる 未来を創る
私たちはこのまちを 子どもから大人まで
共に学び 生かしあう
三学のまちとすることを宣言します
平成23年4月1日制定
佐藤一斎の「三学の精神」を理念とし、市を挙げて生涯学習のまちづくりに取り組もうと都市宣言を行いました。
恵那市三学のまち推進計画と市民三学運動
恵那市では、生涯学習のまちづくりを進めるための「恵那市三学のまち推進計画」を策定しました。推進計画は平成22年度からの5年間ごとに計画の見直しを行い、「三学の精神」を理念に、子どもも大人も高齢者も、「共に学び、学んだことを活かし合えるまちを創ろう」と、市を挙げての生涯学習「市民三学運動」に取り組むものです。
【概要】
恵那市では、生涯学習のまちづくりを進めるための「恵那市三学のまち推進計画」を策定しました。推進計画は平成22年度からの5年間ごとに計画の見直しを行い、「三学の精神」を理念に、子どもも大人も高齢者も、「共に学び、学んだことを活かし合えるまちを創ろう」と、市を挙げての生涯学習「市民三学運動」に取り組むものです。
【市民三学運動】
恵那市三学のまち推進計画を実践するため、「読書のすすめ」「求めて学ぶ」「学んで活かす」の3つの柱をもとに、読書に親しみ、学びを広げ、学んだことを地域社会に活かす「市民三学運動」を展開しています。
【主な取り組み】
読書のすすめ
・恵那市読書の日(毎月第3日曜日)の設置
・読書活動の推進(学校朝読書、親子読書、図書館司書によるブックトーク)
・恵那市中央図書館の充実
求めて学ぶ
・市民講座、出前講座の実施
・先人顕彰事業(下田歌子賞、山本芳翠生誕160年記念事業、三好学生誕150年記念事業)先人学習講座
・「佐藤一斎日めくり」、「恵那の先人30人」の配布
学んで生かす
・市民三学運動推進委員会の設置と市民三学運動推進計画の進行管理
・市民三学地域委員会の設置と市民三学地域塾の開講
特定非営利活動法人いわむら一斎塾の取り組み
21世紀を生き抜く教養豊かな人材と指導者を養成するために、郷土が生んだ幕末の偉大な碩学佐藤一斎翁の教えを基本理念として、広く高い見地から多様な学習と修養の場づくりに関する事業を行い、子供から大人まで幅広い層に至るまでの「人づくり」、「心そだて」及びそれを活かしたまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
恵那市先人顕彰事業「下田歌子賞」(エッセイ&短歌募集)
平成16年(2004)、下田歌子生誕百五十周年を迎えるにあたり、下田歌子にふるさとである旧岩村町(現・恵那市岩村町)が、岐阜県、実践女子学園、PHP研究所の協力を得て、下田歌子先生の業績を顕彰しつつ、エッセイ募集を通して、これからの生き方、考え方、教育のあり方を共に考え学ぶために始めた公募賞。平成15年の第一回募集以来、全国各地から多数の秀作が寄せられており、現在は、エッセイの部と短歌の部で募集しています。
先人顕彰拠点施設 「佐藤一斎學びのひろば」
令和7年10月19日(日)佐藤一斎學びのひろばを開館いたします。この施設は、佐藤一斎と出逢える、対話する施設です。佐藤一斎ゆかりの資料を展示し、その一生や業績を単に伝えるだけの施設ではありません。伝えたいのは、今に生きるその「教え」です。佐藤一斎の教えを学ぶ場として、日本に一つしかない施設を目指しています。
旧字体の「學」を用いたのは、その字形に深い意味があるためです。指導者が学ぶ者の手を取り、立派な大人になるためへと導く様子を表現しており、また、建物の中で教え学び合う姿も象徴しています。教育の本質的な意味と、学びを通じた人間形成の大切さが一文字に込められています。
「ひろば」としたのは、垣根や敷居がなく、誰もがここに寄り合う場になるよう願いを込め、やわらかくやさしいイメージのひらがな表記を用いました。
先人顕彰拠点施設として下田歌子や三好学をはじめ、恵那の先人の生き方に触れる施設として、多くの皆様の来訪をお待ちしております。
また、併せて、郷土資料が充実した学習・研究の場として恵那市中央図書館岩村分館も開館し、新たな「まなび」の場が生まれます。